栄養不足とメンタル不調の関係|心と体をつなぐ栄養学(2025年版)
はじめに
気分の落ち込みや不安感、集中力の低下など「心の不調」を感じたとき、多くの人はストレスや性格のせいだと思いがちです。しかし、実は“栄養不足”がメンタル不調の大きな原因になることがあります。本記事では、最新の研究や日本人の食事摂取基準(2025年版)を踏まえ、栄養とメンタルの関係を科学的に解説し、日常生活で取り入れやすい改善法をご紹介します。
栄養不足が心に影響する理由
私たちの感情や思考は、脳内で分泌される「神経伝達物質」によって大きく左右されます。代表的なものにセロトニン、ドーパミン、GABAなどがあります。これらの物質は、食べ物に含まれる栄養素から作られています。
- セロトニン:トリプトファン(必須アミノ酸)、ビタミンB6、マグネシウムが関与。
- ドーパミン:チロシン、鉄、ビタミンCが必要。
- GABA:グルタミン酸から生成。ただし「栄養不足が直接GABA合成を低下させる」という点については研究段階であり、今後の知見に注目が必要です。
必要な栄養素が不足すると、神経伝達物質が十分に作られず、気分の安定やストレス耐性が低下してしまう可能性があります。
不足しやすい栄養素とメンタルへの影響
日本人の食事調査(厚生労働省「食事摂取基準2025年版」など)では、特に以下の栄養素が不足しやすいと報告されています。
1.鉄分
・不足しやすい層:特に女性(月経・妊娠期)。
・不足すると:疲れやすい、気分の落ち込み、集中力低下。
・多く含む食材:赤身肉、レバー、ひじき、ほうれん草。
2.ビタミンB群(B6・B12・葉酸)
・不足しやすい層:偏食、ダイエット中の人、高齢者。
・不足すると:不安感、イライラ、睡眠の質低下。
・多く含む食材:玄米、豚肉、卵、大豆製品、葉物野菜。
3.オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)
・不足しやすい層:魚をあまり食べない人。
・不足すると:うつ症状、不安の悪化、集中力低下。
・多く含む食材:青魚(サバ、イワシ、サンマ)、亜麻仁油、チアシード。
4.ビタミンD(近年注目度上昇)
・不足しやすい層:日光に当たる機会が少ない人。
・不足すると:免疫低下や気分の落ち込みと関連する可能性あり。
・多く含む食材:鮭、きのこ類、卵黄。
5.マグネシウム
・不足すると:不眠、イライラ、疲労感。
・多く含む食材:ナッツ、豆類、海藻。
6.亜鉛
・不足すると:気力の低下、ストレスに弱くなる。
・多く含む食材:牡蠣、牛肉、カシューナッツ。
腸内環境とメンタルの関係(腸脳相関)
近年注目されているのが「腸−脳相関(gut‑brain axis)」です。腸内環境の乱れはセロトニンの産生や神経伝達に影響し、メンタル不調を引き起こす可能性があります。ヨーグルト、納豆、キムチなどの発酵食品や食物繊維を意識的に取り入れることが推奨されています。
毎日の食事で心を整えるポイント
1.主食・主菜・副菜をバランスよく:極端な糖質制限や偏ったダイエットは心の不調を招きやすい。
2.魚を意識的に取り入れる:週2回以上、青魚を食べる習慣を。
3.ナッツや豆類を間食に:手軽にミネラルを補給できる。
4.腸内環境を整える:発酵食品や食物繊維を毎日少しずつ摂る。
栄養を補うサポート(サプリ・宅配サービス)
理想的には食事から栄養を摂ることが基本ですが、忙しい日々では難しいこともあります。そんなときは、以下のような補助を取り入れるのも一つの方法です。
- サプリメント:鉄分、ビタミンB群、オメガ3、ビタミンDなどを補いやすい。ただし効果には個人差があり、医師や専門家のアドバイスを受けるのが望ましい。
- 宅配弁当サービス:栄養バランスが管理されており、仕事や子育てで忙しい人に便利。
- プロテインパウダー:手軽にタンパク質やビタミンを補給可能。
👉 例:Amazonで人気の「鉄+ビタミンB群サプリ」や、栄養士監修の冷凍宅配弁当サービスは、無理なく取り入れやすい選択肢です。
まとめ
・栄養不足は心の不調を引き起こす大きな要因になる。
・鉄、ビタミンB群、オメガ3、ビタミンD、マグネシウム、亜鉛は特に重要。
・腸内環境の改善もメンタルケアに有効。
・食生活の改善が基本であり、サプリや宅配サービスは補助的に使うのが望ましい。
「心が疲れやすい」と感じるときこそ、食生活を見直すチャンスです。 まずは今日の食事に、小さな一歩を取り入れてみてください。
👉 【あわせて読みたい】
- ストレスに強くなる栄養素まとめ|ビタミン・ミネラルの役割
- ドーパミンを高める食事と栄養素|やる気を引き出す方法
- セロトニンを増やす栄養素と食べ物|幸せホルモンを作る食事法(2025年9月更新)
- 栄養不足とメンタル不調の関係|心と体をつなぐ栄養学(2025年版)
- 【2025年最新版】ビタミンDの効果と摂り方完全ガイド|不足リスクとおすすめサプリ
✅ 本記事は健康情報の提供を目的としています。実際にサプリメントを利用する際は、用量を守り、必要に応じて医師や管理栄養士にご相談ください。
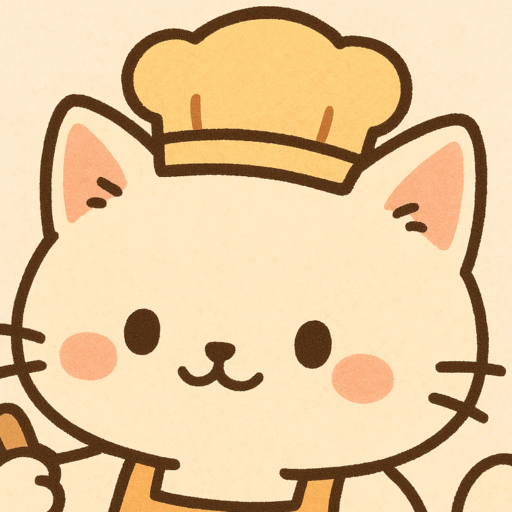
・栄養士
・就労継続支援A型事業所で生活支援員として勤務中
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません

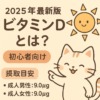





コメントを残す